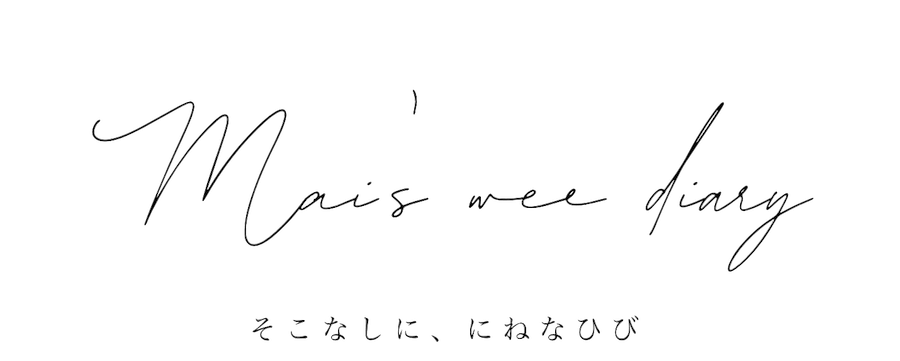ほぼゼロからのスタートで、10年ぶりとなる、勉強というもの。
まさに、LEARNからSTUDYへのスイッチ。
そしてわかること、それは果てしない。
入る量が半端じゃないことに、驚きを隠せない。なぜなら元が空っぽだから。
スタートをきってから5週が経った。
学生を終えたばかりのような若者に混じっての大学受験講座。
まあいわゆるtoeflという英語のテスト。それを受けないと、
大学院には入れてもらえないのだ。
完全に、自分のレベルに沿わないことはわかっていたけれど、私は一番上のクラスにこの身をねじ込んだ。それが私の性格で、そしてやり方だった。
大昔大学に入るときにこんなようなことをやったような気がする、という記憶すら曖昧な
見覚えのあるようなないような内容の文章に、ただ圧倒されて、頭を真っ白にしながら机に向かった最初の数週間。
私は、自慢じゃないが(本当に自慢じゃないな)本を読まない(読めない)人間だったので、日本語で中学生向きの文章でも一冊読み切る自信がない。
そんな人間が、
ほ乳類の生態系のこととか近代のコミュニケーションにおけるなんちゃらビジネスモデルとか政治的背景のアジアとヨーロッパにおけるなんとかとか太陽光システムがどうとか
ウランだとかなんだとか”物理学においてハドロンの一つで*&^%$原子核を構成す@#$%^&
とか英語で言われて、わかるかというと、結果は明白なんである。
つまり、こりゃあ、日本語で言ってくれても、わかんねいよ、っていうね。
だから、”これを読んで後の問いに答えなさい” という読解力のテストで、
後の問いまでたどり着く、よりもなにも、まず、….読めないんですけど….
人類学、工学、生物学、言語学、地質学、歴史、哲学など見事に網羅されている講義をそれぞれ聞いて、自分の言葉でまとめなさいという聴解力のテスト、自分の言葉でまとめるというかなんと言うか、まず宇宙人がしゃべってるとしか思えない…..
そして昔からの一番の壁となる
他のひとびとになじめないという軽い対人恐怖症により、完全に孤立しつつ人をひたすら恐怖に感じる日々を抜け、
制限時間20分を、完全に頭が真っ白になるだけで終わっていたのが、
20分とにかく集中して解読し、問題を解くということが
(何とか)できるようになった。
最初に課題を与えられたとき、何パーセント解けたかとひとりずつ聞かれて、
”全くできなかった”と答えて、”できなかったってどういうこと?”と言われた。
私は、もう社会的には大人の部類に入るとおもうが、できそこないの小学生の気持ちがそのとき誰よりもわかるような気がして、高校生のとき0点をとり続けた公民のテストのこととか、今になっていろんなことを思い出していた。
これほんとに、そのうち解ける日がくるんだろうかと真剣に思ったものだが、
毎日雨が降っても風が吹いてもとりあえず、とりあえず続けていたら、
謎の呪文が次第に知っているものにかわっていくことに気づく。
声に出す、書く、読む、聞く。
この4つをただただ繰り返し、繰り返し、そして
ほんの少しづつ、まさに亀のようなスピードで確実なものにしてゆく。
今までで自分なりのベストを尽くして身につけたウサギの軽薄さと曖昧さの混じる
”使える”会話力を、わたしは自ら完全に白紙にもどした。
わたしは、その時知っていた単語の数で、一生この国で暮らそうと思えばできただろう。そしてそういう英語のはなせない外国人が堂々と胸を張って生きているのがニューヨークという街であって、わたしの好きなところでもあった。
何が起こったのか自分でもわからないけれど、正しく精確な語学力を一から身につけたいとそのとき思ったことは、本当に幸いなことだったと今心の底から思う。
私は今でも、英語が出来る人が出来ない人より偉いなんてこれっぽっちも思っていないけれど、ただただ一つ新しい単語を覚えたことで、世界が100倍広がってゆくことを知った。それは、まさに、素直に”感動”なのだ。
今年に入って、身のまわりで、大切で大切にしていたものたちが次々と
大きく音を立てて壊れていく。どうしてこんなにも同時に失うだろうと
そうやって思い続ける中で、ただ、静かに目の前に姿を現す私の知らない知識達だけが今の私を細い骨組みで支えてくれている。
ひとつひとつは、マッチ棒みたいに小さい棒だけれど、それが、私を、
絶えず着々と前に押し進めてゆく。
わたしは、どれほど自分が無知であるかということを毎日甚だしく心に感じて、
本当に幸せをかみしめている。
小さな頃から無限に湧き出る宇宙への疑問とそして絶えない好奇心を、
こういう形で一生満たしてゆけたら。
もうしばらくして、世界の彩度があがってきたら、
外にでて写真でもとって、ニューバランスの靴をはいて公園にジョギングにいくんだよ。
2、3にちまえに、種をまいたよ。葱だよ。生えるかな。もう枯れたかな。
チャクラがまた開いてゆくその様子といったら、
それはまさに優しくて大きい花のよう。
そして一度閉じてまた開くときは、
当然前よりも成熟していてそして豊かになっているはず。
目にみえないほどかすかに。