電話口の向こうで、
彼はつぶやく。
「カメラの電池なくなって、
充電どこにあるかわからんしそのままやねん。」
◯
わたしと彼は、一年とすこしの間一緒に暮らしていて、
彼は私がいないと
靴下がどこにあるのかもわからないような人だということは、良くわかっていた。
一緒に暮らす男女間において、とても、よくあるハナシだ。
私はそれを、いきがいのようにして生活をしており、
好きだったグレープフルーツの薄皮を毎日のようにむいておくことも、
彼の使うボディーソープを買い置きしておくことも、
替えのパンツを探しに男性用下着コーナーを徘徊することも、
全てわたしの喜びだった。
だから”シーツどこ?”とか、
”うちにまだ醤油ってあんの?”とか電話がかかってくると、
その度に私は、自分の責任を放棄しているような気さえしていた。
数週間ものあいだ、わたしは彼と話さずに、
ずっと色々な感情をずるずると
引きずって
新しい部屋で、ひとり
暮らしていた。
私のキーケースには、変わらずに
前の部屋の鍵がついており、
いつでも勝手に帰ることができるということが、
私をどこにも動けなくさせているのはわかっていたけれど、
とてもじゃないが面と向かってgood-byeというなどという
考えるだけで恐ろしい行動をおこす勇気などなく、
見てみぬフリをして過ごしていた。
忙しい毎日で気を紛らわせて、このまま何事もなかったように振る舞うことも
もしかしたらできたのかもしれないけれど、そろそろ前に進めという
たくさんの出来事やメッセージの中で、
遂に決心をした私は、何週間ぶりに
1ラインの電車にのって、マンハッタンの外れまで夜遅く帰るのだった。
「ひさしぶり」
と中途半端にふたりとも笑って、
ドアの前で突っ立っていた私に
彼は「入れば?」と言った。
抱き合うこともしない不自然さと距離が、寂しいという感情ももはや
ずっと前に通り越して奇妙というしかない。
彼は風邪をひいてぼろぼろで、
ふたりとも笑っていたけれど
とても平気だとはいえなくて、わたしは、
とても、
残酷だとおもった。
わたしはもう、彼のために好きな物をえらんで料理をすることも、
彼が喜ぶだろうとおもって何かを買ってくることも、
彼が必要としているものを与えることも、
出来なかった。
彼は、わたしを初めて抱いた夜よりも、
わたしが泣くのを止めなかった苦しい時期よりも、
わたしを恋人にしてくれた最も嬉しかったあの日よりも、
どんな時よりも優しく、わたしの身体に触れた。
わたしたちが離れてからした何度かのセックスは
もはや彼の義務感すら感じて、
忙しい日々のなか一緒にいて、とても愛されているなどと
感じることはなかったけれど
それは、わたしの完全なエゴのせいだったと
今はわかる。
彼は、いつだって
やさしかった。
はじめてであったときからずっと、
どんなわたしのわがままにも耐えて、
どんなときもわたしの好きなものをおみやげに持って帰ってきて
自分の誕生日なのに私に高いチョコレートを買って来てくれて
おいしいものをめいっぱい食べさせてくれて、
どんなに疲れていてもわたしが夜中に泣いていたら起きて慰めてくれた。
彼は「働かんでも、なんもせんでも、ただここにおったらええ」と
わたしが自分の中心をみつけられずにもがいていたときも、
「おれをマイの中心にしたらええ」と、
「ただ、笑っとったらええ」と
幾度となく私を救ってくれて、
そして彼自身がぶれることは決してないように見えた。
最初から最後まで、嬉しいときも悲しいときも寂しいときも悔しいときも
楽しい時ですら四六時中泣いていたわたしは、
自分のことしか考えていなくて、
彼がどんな風に感じているかとか、何を考えているかなど注意を払ったこともなく、
実際彼にはわたしなど必要いんだろう、彼はとても強いひとだから、
と卑屈になっていた。
寂しくて、ずっと一緒にいるのに死ぬほど寂しくて、
わたしは、
ひとりになることを選んだ。
身体が離れ、次第に心が離れたころに、彼は
「寂しいなあと」つぶやいて、
「一緒に引っ越そうか」と聞いて、そして、
わたしを抱きしめた。
彼は、
「おれ、ずっとまいといっしょにおったから、
休みにひとりでどこいったら
いいか全然わからんくて」と言った。
わたしには彼がひつようだった。
彼がいなかったら、死んでいたとおもう。
でも、だいじなところといえば、
彼が、どれほどわたしをひつようとしていたかなど、
一緒にいて一切考えようとしなかったのが、
わたしだったということだ。
彼は、ごはんが食べられないといって、やせて、
あたまがずっと痛いといって、風邪をひいているのに、
わたしはもう、この一番上手な料理の腕をふるって彼が元気になる
ごはんを作ることも、できないのだ。
わたしのすべては、彼だった。
だから、最悪に皮肉にも、彼をうしなったわたしのからだは空っぽで、
かぎりなく多くのものが入り込んでいる。
あたりまえかもしれないが、
一緒にいたら、絆というものが出来てくるんだとわかる。
おいで、と言って、彼は、わたしの顔を優しく撫でて、
抱きしめて、わたしは、涙があふれてとまらずに、
「こうやって、触れて欲しいって、何もいらないから、ただキスしてほしいって、
ずっと思ってたんだ。」と言った。
彼は、「ごめんね。」といって、
わたしは、「ごめんね。」といった。
わたしたちは、とてもいいカップルだった。
とてもちゃんと好きあっていて、
楽しんでいて、もちろん喧嘩も大変なことも
たくさんだけど、とてもすてきなカップルだったんだ。
わたしは机のうえに鍵をおいて、
そうしてまた最後の最後までこうして泣きはらした不細工な顔で
玄関に立つと、彼はいつもわたしがシゴトにいくときに
見送ってくれるのとおなじように一緒についてきた。
わたしは彼のあんなに寂しそうな顔を見たのは一年以上いて初めてだった。
息をするのがやっとで、言葉など出て来ず、
彼はわたしの頬をそっと確認するみたいに撫でて、
わたしは彼の髪をそっと確認するみたいに撫でて、
“ごめんね”と吐息くらいの小さな声を漏らして
帰った。
大好きだったhillside ave のアパートは、ビルの工事が終わって
こんなにも綺麗な景色だったっけと思うような変わりようで、
昨日は一日真夏日で強い日差しだったのに、
一晩たって家をでたら、
違う世界にいるみたいに凍えそうな気温だった。
春にであって、何度か季節を供にまたいで、暑いときから寒いときと、
そうしてまた春を一緒に迎えて今度はひとりの秋を過ごしている。
外は寒くて、乾燥している。
曇り空の下を歩いたら、
なんだか頭がくらくらした。
飼い主とペットの関係からはじまった彼とのはなしは、
そんな秋の一番いい時期に、
エンディングを迎えてしまって、
本当は、ハッピーエンドになるはずだったんだけど。
彼がねむっている間に、
わたしは机の引き出しの3段目から充電器を出して、
カメラの電池をセットした。
わたしたちの未来が、すぐそこに
どうかきらきらと光っていますように。
恋するNéné
B.C.
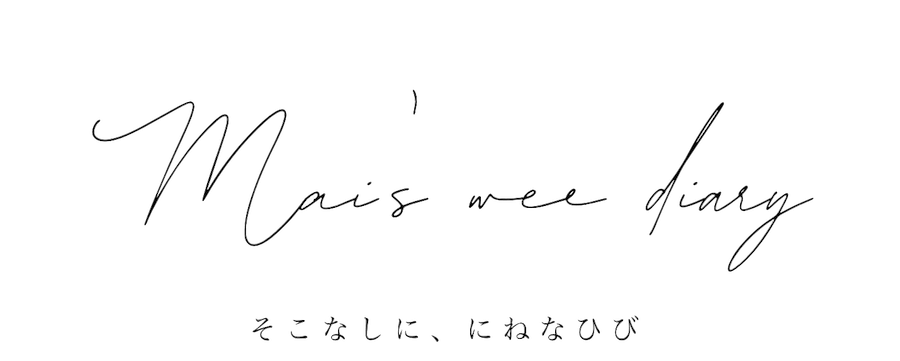

No Comments