雲ひとつない、青空だった。
強いひかりに、ブルーのTシャツは飛び込んだ。
安心する顔に、小さな声で、挨拶をした。
そのひとを、恋しく思った。
大好きな場所にいた。
夜は、眠れなかった。
あるひとが、教えてくれた。洋食やを営むお母さんが
おいしくなあれと魔法をかけたごはんは、本当に美味しくなるんだ、と。
オーダーは、入らなかった。
ずっと、外の陽気を感じていた。
料理は、あまり、楽しくはなかった。
日曜日は、休日で、間違いはなかった。
ドアの向こうは、天国だった。
アイスコーヒーの底に沈んだ砂糖は透明で、甘く、
美しい、朝だった。
わたしは、その肩の不思議なアザに、優しく触れた。
愛する人に、囲まれていた。
余分なことを、期待していた。
前世は、女だった。
料理を、しなければ、と思った。
バス停に腰掛けて、白いボールに山盛りの野菜を食べていた。
わたしは天に、彼らに守られていた。
疲れていた。初めて外国人に話しかけられたみたいに、ぎゅっと縮こまった。
下らないだけの話を延々とする。
文句なしに、全員好きだった。
遂に、あたらしい出会いもあった。
空はいじわるなほどに、澄み切っていた。
自信などは、これっぽちもなかった。
いつも平気なふりで、背伸びをしていた。
今好きなひとを思い浮かべながら、好きだったひとと歩いた。
完璧な色と温度の、ブライアントパークだった。
電車は、うちまで届かなかった。
この身と自分の国と言葉を、誇りにおもっていた。
10年すごしたNew Yorkを、離れようかと彼は考えていた。
変化は、つきものだった。謙虚なきもちを思い出していた。
大切なことを、教わった。
完璧に優しく完成された美しい日だった。
魔法使いのお母さんは死んだ。
月が昇るのを待っていた。
今日程の日は、みたことがなかった。
幸せだった。
まだまだ、はじまったばかりだった。
人を、もっと好きになって、この身と心を全て預けたいと思えた。
私は、手を合わせ、空の遠くのほうへ祈り涙を流した。
夏が来て僕等。
火花が散っていく匂いと幻。
肌寒い初夏の果実をあびるようにもぎとる。
消えゆく。
疲れているはずなのにねむくなかった。
月灯りに照らされた夜の坂道を
彼を思いながら小走りに下って、
逢いに行く誰かがいるという幸せを感じていた。
しんと静まり返った朝から熱っぽい夜を、
通して早送り気味に流した。
2009年の料理をしていたときの日記より
Néné B.C. in New York
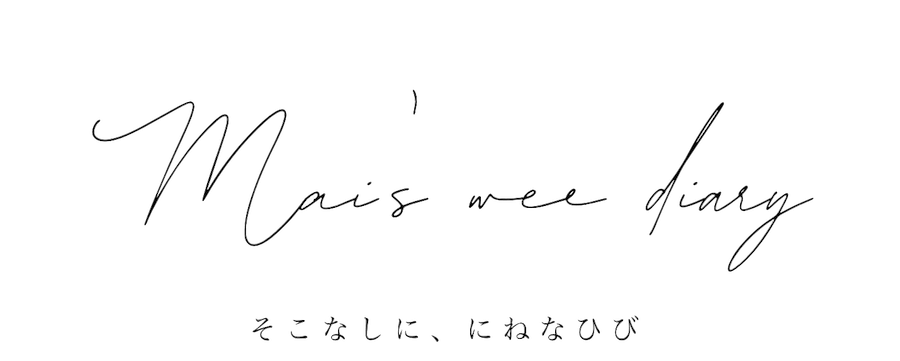
No Comments