わたしは相変わらず、崩れ落ちるように、または床に全身磁石でくっついているようにして、その床に伝う涙と鼻水で洋服をビショビショにしながら、泣いていた。
あまりに苦しく、分からないことがこの世界には多すぎて、その瞬間、とくに分からなかったことが、
なぜ、ひとは、一番愛しているひとと一生を共にすることを選ばないのか?
一番愛しているひと以外のひとと、家族でい続けるということは、一体、本当に一体、どういうことなのか?
といったことだった。
わたしは家族の愛と、恋人の愛の違いのことを学びつつあった頃で、いろんな形の愛が、同時に複数常に転がっていることは
あたりまえに理解ができるようになったけれど、
それにしても、運命とは、数奇すぎると感じた。
本当は愛し合っている2人が離れ離れになり、そして別の相手と結ばれることを受け入れるには、あまりに愛は深すぎて、
それでもそこに転がるいくつもの違う種類の愛たちがそれぞれ交差し、美しく折り重なる糸の様子は、とても偶然できたとは思えないほど精巧で、いつかの過去生から続いているストーリーは
結ばれようが結ばれまいが、ただそこに一本ずつ織り込まれてあるだけでとても綺麗な気がした。
そしてわたしはそれをそれとして、受け入れて、一番愛しているひととの家族を、諦めなくてはいけなくなった時、ビショビショに突っ伏していたのだ。
そのときふと、目の前に現れたひとがいた。
そのひとは、わたしのことを、よく知っているようだった。
縮こまって顔も見えずにいるわたしを前に、
「相変わらず、面倒くせえやつだなあ。」と言った様子で小さくなったわたしを見下ろした後、目の前にゆっくりとしゃがんだ。
わたしは、ぐしゃぐしゃのまま、泣きじゃくりながら、それを、そのひとに最初に出会った時からずっと、たったひとつだけ
聞きたかったことのように聞いた。
「ねえ、教えて?」
「どうして、ひとは、一番すきなひとと家族にならないの?」
「どうして、一番すきなひととの、家族を諦めるの?」
「教えてよ…
一番すきなひとじゃないひとと、家族になるって、どういうこと?」
そのひとは、じっと、
黙ってわたしの質問をくみ上げて、一拍置いてから、
こう言った。
「じゃあ、俺とやってみれば?」

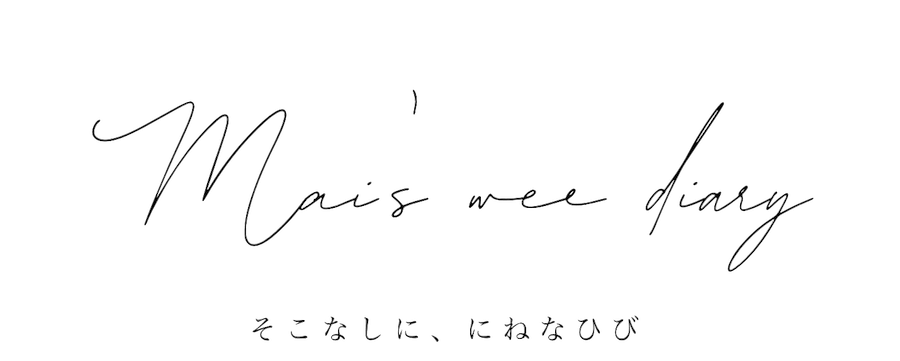

No Comments