ドアを開けると、そこには見慣れた大男が立っていて、そもそも私にとってイタリアという国がオシャレなのかそうではないのか、がイマイチつかみきれない感じはあるんだけど、その男もまた同じだった。
多分、イタリア人にもお洒落な男とダサい男がいるはずで、そのイタリア男に限ってはその絶妙なギリギリラインの上を行くところが結構好きだった。
明らかにセンスがいいとは言えないが、明らかにセンスが悪いとも言えない。
彼の服装やメガネや帽子や出で立ちが、果たしてお洒落なのか否か。
それは誰にもわからないし、自分もまたそういう立ち位置を死守するのがいい。
というわけで、彼がその日どんな服装をしていたのかは全く覚えていないのだけど、いつものこざっぱりしたneatなシャツと優良企業に勤めるサラリーマンさながらに整った髪、一流大学に通っていそうな雰囲気の眼鏡が私を迎えた。
あ、もしかしたらエプロンをしていたかもしれない。
なぜなら彼はその頃私と同じ自分さがし真っ最中のミュージシャンで、ギターと歌声は間違いなくセンスのいいだけじゃない重厚感もある確かな才能だったのだけど、そのあと国に帰ってなにをしてたかというと、料理の道に戻っていたのだよね。
名前の知らない有名な料理の学校に行くことにした。と聞いた時は、両手をあげてひとり跳び上がった覚えがある。
なぜなら彼の作る食べものはまた、ギターの音色よりもさらにはるか上に抜きん出ている確かさと重厚感とセンスに光っていたから。
問題はその卑屈でネガティブな性格と、お洒落なのかダサいのかよくわからないサスペンダーだけだと思う。
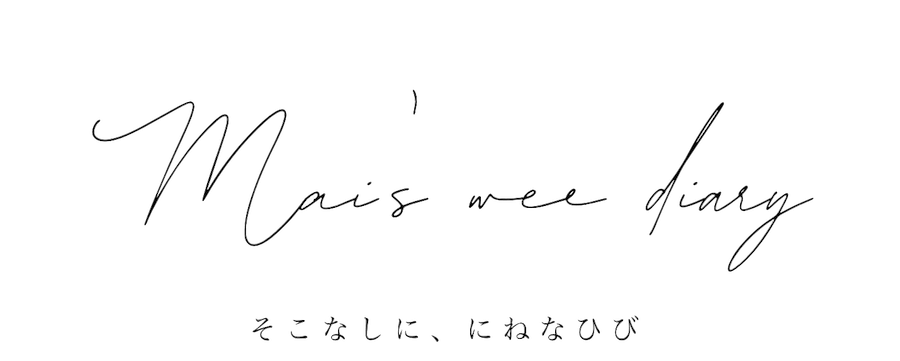
No Comments