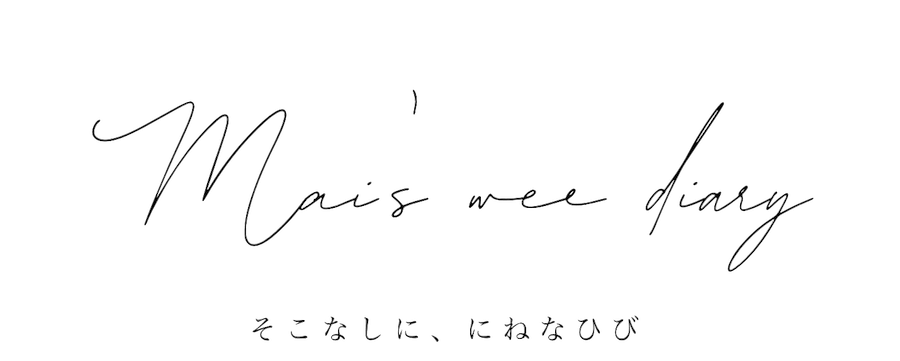おおきな薄暗くて神聖な学校みたいなところで
ぼくは大勢と暮らしていた。
勉強をしたり、しごとをしたり、恋をしたり。
そこでもぼくは、純粋で、まるでグッドドクターのショーンのように立ち回っていて、リアみたいに優しくキスをしてくれる女の子や、つっかかってくる子、爆発していじわるをしてくる子などがたくさんいた。
ある日は、ぼくをみた女の子に突然罵倒されて、とてもとても怖くて恥ずかしかった。ある日は、ぼくが他の子にやさしくしたら、ある男の子に酷いことを言われて、とても混乱した。
ぼくはたくさん泣いて、いつも小さな部屋に駆け込んで、もうみんなとは一緒にべんきょうしたり、過ごしたりできないみたいだった。
悲しくて、つらかった。
でも、おそらのうえからみんなをそこで観察していると、あるときその男の子がお母さんに話にいくのが見えた。
「ぼくは、だれかが素晴らしい行いをしているときに、どうしても酷いことを言っちゃうんだ。」とそう言っていた。
それをきいて、ぼくは、自分がしたことがダメだったのではなくて、良いことだったことに気づいた。
そして、意地悪をいってきた女の子も、もしかしたらきっと同じ理由だったのかもしれないとそう思った。
ぼくは苦しくて辛い毎日だけれど、みんなも別の意味で、いろいろなものを抱えて生きている。よわい。
ぼくは、いろいろなものを抱えることを勇気をだして手放して、つよくいるから、抱えながら生きるみんなのことなんて、嫌いだだった。
なにもせずに、ひとを傷つけることでしか、自分を守れないなんて。かなしいとそう思ったんだ。
でも、それも含めて、ぼくはこの世界に生きている。
ひとりじゃなく、みんなとともに生きていて、悲しいこともあれば、そんなみんながいるから、胸がはちきれるほどときめいたり、はしゃいだり、最高に感動することもあるんだってこと。
ぼくはもういちど教室にもどって、べんきょうをはじめた。