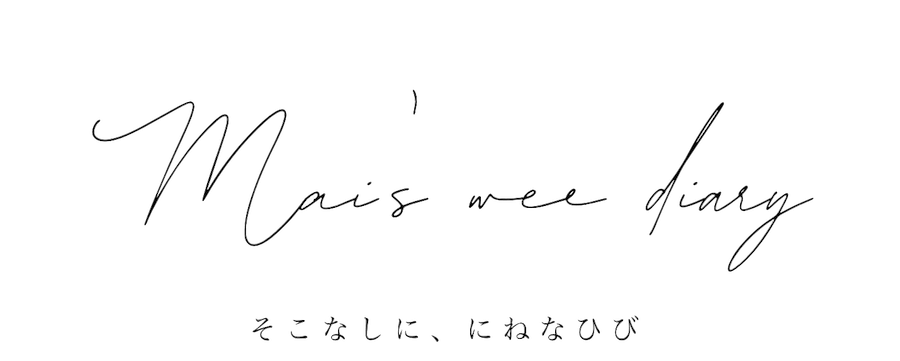あの日 まだほんの肌寒い春の季節に
飛行機の飛んでいない空港で
わたしはどこか遠くへ行こうとそう思った。
前日から、生花でコサージュの飾りを作り、水色のズボンのつなぎの服は、肩の部分が透けて腕に可愛い刺繍がしてある洋服で、それを着て、コサージュをつけて、タオ君の入学式に行く予定だった。
式の当日の朝に、お化粧や髪の準備ができなくて、たった5分誰かが段取りを助けてくれていたら、100パーセント十分に間に合う時間だったその晴れの日に、わたしは家族に「無理していかなくていいよ」と置いていかれ、パニックを起こした。
ほんのささやかな助けだけで、たった数分、今が何時で何をすればよくて、どう間に合うかを、ほんの少し当たり前のことを、教えてもらえるだけで、私はタオ君の入学式に参列できた。
タオ君にも家族に置き去りにされたわたしは、もうどうしていいのかもわからず、何もかも準備万端にしてもらった後の、直前の出来事で、私はピカピカの新入生の胸に挿そうと思い作っていた、自分とお揃いの胸の花の飾りを握りしめて、裸足のまま家を飛び出して学校に向かった。
パニックを起こしたまま飛び出たので、文字通り裸足で車に乗り込み、事故スレスレで小学校の駐車禁止場所に停車し
静粛な雰囲気の体育館に、ズカズカと殴り込むような気持ちで、裸足のまま乱入した。
新一年生も、保護者も全てきちんと着席していて、誰か知らない先生が厳粛に祝いのスピーチが響く静かな体育館だった。
全員の訝しげな注目の中を横切って、ひとつだけ空席を見つけた。
わたしが座るはずだったその席の横にちょこんと座っていたタオ君がいた。
そこまで目がけて競歩のように裸足のまま近づき、その花を彼の胸ポケットに乱暴に挿した。
そしてわたしはそのままズカズカと体育館の群衆をもう一度横切って、外に出た。
家に戻り、パスポートと通帳だけ握りしめて、スーツケースにありったけの生活用具を詰め込み、もう2度と帰らないことを決めた。
遠い遠いどこかの国の果てで死ぬつもりで、姿を消したのだった。
ところがはるばる空港に着いて飛行機に乗ろうとすると、
飛行機は一本も飛んでいなかったのである。
がらんどうの静かで人もほとんどいない空港の、フライトスケジュールのパネルを何度も目をこすりながら眺めた後、念のため誰かを捕まえて、飛んでいないことを確認した。
ほんとうに見事に一本も飛んでいなかったので、わたしはどこにも行けなくなったのだった。ターミナルという映画の、空港に缶詰になって暮らす主人公になったみたいな気持ちだ。
一応泊まる場所があって、ホテルにチェックインし、通帳の中のお金で何泊くらい泊まれるんだろうと、苦手な計算を3秒くらい頑張って諦めた。
外国の山の奥ならまだしも、空港で死ぬのも縁起が悪く気が引ける。
どう死ねばいいのかもわからないまま、友人や家族から電話がひっきりなしにかかるのがどうしようもなく苦しくて、まず携帯の電源を切った。
ただ、小さなことを最初に助けてもらえれば、それで困ることは一度も起こらない場面で、誰にも気づいてもらえない。地獄のように苦しく、それは数年経った今でも続く。
近くに住む母は、そして一生かかってもあんたを理解することはできないとそう言い切っていた。
わたしはただ普通に愛する息子の入学式に参列したいだけだった。
洋服や段取りを前日に支援の友達が何から何まで用意してくれて最後
当日の朝だけは、時間がほんの少しずれて、助けが無く、しくじったのだ。
何日も、空港に居た。
静かで人のいない空港の中を、気の向くままに歩いた。
桜が散っている時期で、外を散歩すると、とても優しい風が吹き、残った桜の花びらが落ちてゆく美しい季節だった。
なにもかもから解放されて、わたしはその場所では日本人でも何人でもなく自由だった。
次第に落ち着いてくる気持ちは、結局行き場もなく、繰り返しパニックを起こしては、誰にも助けてもらえない苦しさも、タオ君への顔向けもできないまま、わたしには帰る場所などどこにも無いように感じた。
それから時々携帯の電源を入れると、見慣れない番号から繰り返し着信があるのに気づく。
何年も連絡がなかった人からだった。
留守電を聞くと、「まい、どこにいる」
その人肌の温度の声が、小さな四角い電子機器から耳に響いた時、数年前に付き合った山下の声だとわかった。
どこにも行き場を失った自分の存在に、その声が心の奥まで静かに届き、
この世界に生きていていいのだと初めてそう感じた。
その時家族から数年ぶりに連絡をもらい、マイの消息を訊ねられて、捜索願いを出され、死んだと思われたわたしに、繰り返し繰り返し電話を鳴らしたのが、たった1人、山下だった。
わたしはそして、その後、家に帰ることができた。
迎えが来て、俯いて誰とも話せなかった言葉が出ないわたしに、改めて電話が鳴った。
柔らかい、鼻にかかった中位のオクターブの、山下の声だった。
「空港にいたの?」
「うん」
「なんで空港に行った?」
「ひこうき、乗ろうとして」
「うん」
「でもォ、とんでなくて、のれなかった」
涙ぐむわたしに、数年ぶりに連絡した彼は
何事もなく子どもをあやすように、
「うん、また今度一緒に乗ろうな」
とただ一言そう言った。
わたしはそして家に帰り、あの時山下から連絡が来ていなかったら、死んでいたかもしれないなといまでも思う。
あの日、わたしは本当に死のうと思って家を出て、外国に行けば、もしかして生きられる場所が必ずあることを知っていた。
どこでもいい、行ったことのない国でいい、死ぬ場所が見つかるのでもなんでもいい。
ただこの国では生きる術がない。
ただ日本を出たかった。ずっとどこにも居場所はなく、誰にも助けてもらえない場所で、たくさんの特性を抱えながら生きることができない。
でもその時のわたしの頭には、山下の顔が浮かんだ。
日本でもいいから、山下のいる場所なら生きられるかもしれない。
大事なひとの、側に居たい。
素直にそう思ったのだ。
とても鮮明にそう感じたことだけを、空港のホテルの部屋の窓からの景色と共に、よく覚えている。
あの日の空港の春の空も空気も静けさも、電話越しに響いた優しい声が、自分の生命を救ったことも、山下はとうの昔に忘れても、私はきっと一生忘れないだろうと思う。
(今日もファミリーマートで山下に救助され。2024/6/29)