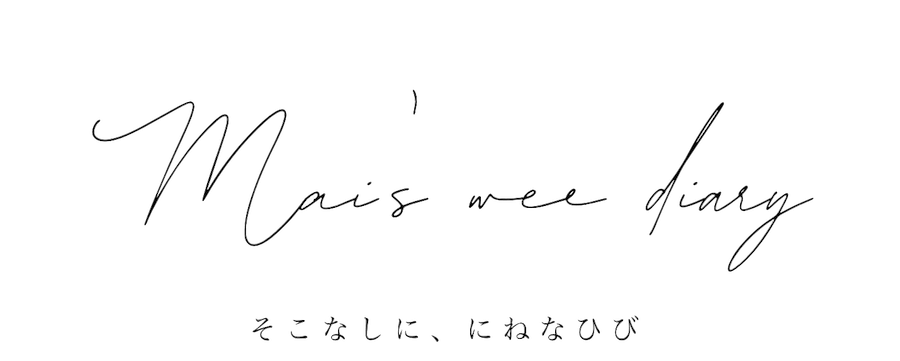この世界の、絶望という絶望の化身のようなわたしが、それを脱ぎ捨てるとき
それは、この世界における絶望という絶望すべてに対して、愛を持てるときだった。
海の底に沈んだ人型の鉛
海藻と苔に覆われた何百年も前に沈んだ重たい重たい鋼鉄の船のように、それは魚や深海の生き物たちの棲家となった。
抜け出た泡のような軽やかで光る魚は、つぎつぎと自由に泳いで、重たい海の底など感じさせぬような、そんな艶やかな動き
海の底に沈んだ絶望の化身を、つっついて、可愛い、美しい、と物珍しいふうにそれを眺めて、そこにはリトルマーメイドが人間のフォークを集めていたときのような、心からの愛があった。
そして、その塊は、自分と同一体だったのが、まるで肉体から魂が抜けるように自由になると、苦しみや痛みは、一切感じない代わりに、同調も共感もしないまさに祝福と自由と楽さがそこにあって、そこで分断されたのかとおもいきや、起こったことは
この世界には、わたしが体験せずとも、やまほどの絶望や苦しみに満ちている。それが、なんて幸せなことなんだろうとそう感じる不思議な光景だった。
つまりわたしは、鉛の塊の痛みそのものでありたかった。それは見通しがよく、絶対に変わることなくそこにあって安心であり、この世界を害するように見えて、この世界のありとあらゆる絶望に通じており、それは愛そのものだったからだった。
ただ問題は、肉体がもうそれを請け負うのに追いつかないという事実。
そして、そろそろその絶望を卒業せねば、もうどこにもいけないことがうっすら理解できたからだった。
わたしは絶望の化身でいたかった。
それがわたしだった。
これほどにネガティブな存在はこの世界に存在しないであろうというほどに、わたしは悲しく365日絶望していたかった。
なぜなら、喜びや祝福は誰もが欲しがるものであり、でも、この世界でどうにもならない絶望や悲しみは、誰からも愛されずに煙たがられる存在であることを知っていたから。
自分だけは、そこに完全に寄り添っていたかったのだ。
そしてわたしは文字通り、絶望の化身となった。
今回、それを脱いだときの安堵は、ようやくそこから抜け出せるというような軽薄なものではなかった。
ただただ、絶望と苦しみへの純粋な愛と、それがとてもこの世界を形作るにあたって美しいものであることや、わたしが絶望でなくなったとしても、まだこの世界には溢れるほどの絶望の化身のような世界がずっと、消えずに残っていることが、安堵と喜びと嬉しい、ただ幸せであるという事実だった。
この世界が、癒やされて愛に向かい、そのような悲しみや苦しみと無縁の世界に向かってほしいという一心で、セラピストという仕事に向かい合った。
そして、それが実際に起こることを誰よりも熟知しているからこその、絶望をそのままにはしておけないという苦しみ。
それが終わりを迎え、絶望の化身として生きてきた自分は行き場を失ったところで、今日の解放だった。
絶望は、美しい。
それを進んで請け負うことはもう無い。必要がないからだ。
でも、たとえこの世界に絶望して苦しみ抜いて、幸せや喜びを掴み取れない不幸なひとたちがまだ山ほど存在していたとしても
それでもこの地球という星は、まだとてつもなく美しいとそう感じた。
深い青と緑に包まれた、真っ白で真っ青な星。
そこには喜びと祝福があり、
同じくらいに絶望と苦しみがある。
そしていつか、その世界から絶望と苦しみが消える日が、いつか、何万光年か先に訪れたとしても、きっとこの星はさらに美しい。
わたしはもう、彼らの痛みや苦しみに、同調することで愛を提示しなくてもよくなった。
共感して涙を流すこともしなくてよくなった。
ただ、そこには純粋な愛がある。
それが美しいものであることと、すべてを含めて、それでよいのだということ。
変わらなくていい、そのままでいい、傷つけ合い、命を危険に晒してもよい。
それも含めて人間として生きるすべての経験をわたしたちは全うしており、その中で喜びや祝福の価値や愛に目覚めたひとたちは、そう生きればよい。
わたしはもう、誰にも傷つけられることはなくなった。
誰にも足枷をつけて海の底に鉛の姿で鎮められることもなくなった。
ただただ自由におおきな海を泳いで、光の中で色とりどりの世界を楽しむチケットを手に入れた。
誰かが死ぬほど苦しんでいたとしたら、助ける。
でも、同調はしない。
できることをして、わたしは自由にこの美しい世界を描いてそして、海の底の絶望の化身だった自分に生えた苔をたまにつっついて、やっぱり美しいなあと見惚れる。
この世界のありとあらゆる絶望は、怒りだったけれど、脱いでもまだまだこの世界には山ほどの絶望があるんだ。
なんて愛おしい。
思っていた祝福とは全然ちがったけれど、絶望自体が美しいものであり祝福であるというふうには思っていなかったから。
それもやっぱり、ものごとにはすべて裏と表が一体であり、光と闇は同じ存在であるというワンネスそのものだった。
絶望を抜けて祝福に行くのではない。
絶望自体が、祝福なんだ。
これで祝福の香りのコンセプトが決まりそうだ。
ニモっていう名前にしようかな。
そして、色鮮やかで自由でスパンテイニアスな香りで間違いない。
グレープフルーツをふんだんに使おう。
楽しみだ。