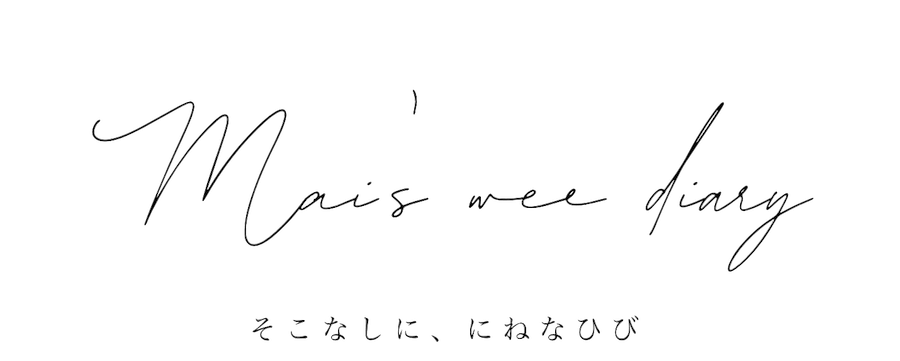”ごちそうさま。”
という自分のノドから発せられた音が、
部屋全体に響いた。
この部屋で、この台所で火をかけて何かをこしらえ、
そして食べる、最後の食事。
空は暗く、一日中清々しい夏日の後の、
静か、でもないいつもの夕暮れ。
ひとが、生まれかわるその前というのは、
ほんとうに死んだような感じがするのだなあと
その皿を前に
一切食欲がわかないまま
ただ口にそれを押し込みながら
考えていた。
ひとは、動くために、明日生きるために、
エネルギーを必要と、する。
エネルギーを摂取したから、動くのでは、ない。
水分さえしっかりとっていれば、
ひとはとても小さな量のカロリーをとるだけで、
むしろ効率よく動くことができるのは言うまでもないけれど
瞑想の10日を何度か経験するなかで
ひとは毎日、頭をつかったり、
喋ったり、何かを読んだり、
そして動いたりしなければ
著しく摂取量が減って
ほんとうに微量しか、
からだはエネルギーを必要としないのだという
あたりまえそうい聞こえることを、
わたしはこの身体を通して
学んだ。
「死ぬ前にひとつだけ食べるとしたら、
何が食べたいか」
という質問は、そんなわたしにとって
愚問以外のなにものでもないので、
この先できるならば
このように訊ねられる機会に出くわさないことを
祈っている。
そんなことを思う、夜に、
わたしはやっぱり、Thin spagetti にキャベツを絡めた
アーリオオーリオを食べる。
最後、空っぽになった部屋は、
ほとんど、自分がそこで生活をした形跡を
消すことに成功して、
いよいよ、自分は、
この場所から
いなくなるのだと、
淡々とした様子でいる。
最後の一日は、ニューヨークで暮らした6年間で
よく足を運んだ店へ
ぽつりぽつり、訪れた。
West 4のちかくの、ジュエリーのお店のショウウィンドウに、
クリスマスに買ってもらったネックレスと
お揃いのピアスが飾ってあった。
とても繊細なデザインで、それが好きで、
いつまでもそこに立ってみていられる気がした。
友達や、自分の誕生日に、何かの度に
毎回ケーキをオーダーした小さな職人のペストリーで、
コーヒーのエクレアをかって、
普段買ったことがないような
カプチーノを頼んでみて、
その先の三角公園に腰掛けて
人々が日曜日の午後のとてもいい季節を
心の底から楽しんでいる様子を
眺めた。
となりに座っていた女のコは、
英語の小説を、
読んでいた。
とても満足して、”家”に戻って、
最後散らばったレシピとかノートとか、
いるものだけ抜き取って、
あとはゴミ袋3袋くらいになって、
本棚は空になった。
スーツケースにほとんど詰め終わったところで
彼の、おとうさんとおかあさん宛に
「やさしくしてくれて、ありがとう。明日、出発します」
とのメッセージの手紙を、書いた。
鍵を、彼への手紙とともに、残す。
日本語で書けば、他のひとには理解できないけれど
彼にはわかる、いつでも暗号のように
わたしは自分の言葉をつかっていた。
封筒にいれなくても、そこに置いておいて、
誰の目に留まっても、そのメッセージは
彼にだけ、届く。
彼が、日本~台湾から戻って、この空っぽの部屋に帰って来るところを
想像した。
冒頭に、
「おかえりなさい。」と、書いた。
大好きだった元主人と、
一緒に朝ご飯をたべたテーブルで、
しずかに、
のど元まで色んな気持ちが
溢れて上がってくるのを
ぐっとこらえながら
キャベツを無理矢理流し込んで、
食欲は一切なかったが、この一皿が
いつもどおりきちんとバランスの整った味付けに
なっていることは食べなくてもわかった。
これをまったく同じ材料で
まったく同じ手順で
日本でまた作っても、
絶対に美味しくないのは
本当に一体何故なんだろうと
いつもおもいながら、
皿は空になって
”ごちそうさま。” と
告げたそのとき
全ては、
終わって、
この部屋へ、
彼へ、
全てのお世話になった人々へ、
世界へ
ごちそうさまでした
いままで、
おせわに、
なりました
と
伝えたような
気がした
笑っている、
彼も
一緒に手を合わせて
”ごちそうさま”と、私の作った料理へ
言ってくれた気が、
した。
旅が、長い旅が、終わろうとして、
胸から首にかけて
ぎゅっと何かに掴まれ締めつけられ
むせ返るような情動とともに
ほっと安堵の影もみえることに
わたしは
胸を、
なでおろしている。
”ごちそうさまでした。”