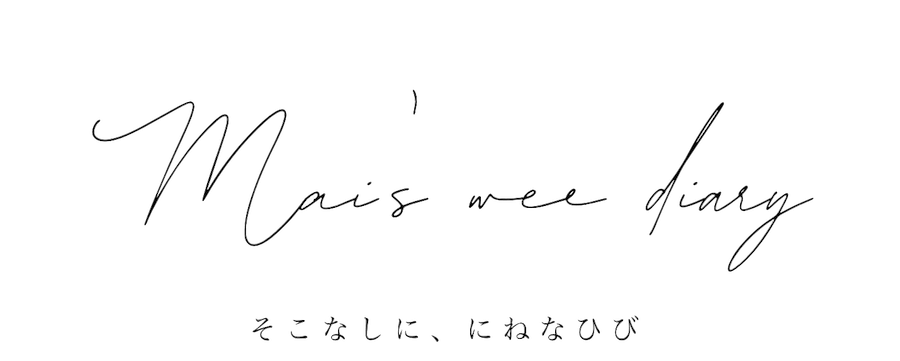ドアを開けると、そこには見慣れた大男が立っていて、そもそも私にとってイタリアという国がオシャレなのかそうではないのか、がイマイチつかみきれない感じはあるんだけど、その男もまた同じだった。 多分、イタリア人にもお洒落な男とダサい男がいるはずで、そのイタリア男に限ってはその絶妙なギリギリラインの上を行くところが結構好きだった。 明らかにセンスがいいとは言えないが、明らかにセンスが悪いとも言えない。 彼 […]…
いわゆるスーパーのフードコートというか、カフェとかというよりも もうすこし、セルフサービス的な空間がとても気楽で好きで、 そこがたまたま所帯染みてなかったりすると、何時間でもその場所にいたくなる。 こぎれいで整ったカフェでも、すてきなレストランでも、ホテルのティーラウンジでもなく、 かといって、学生食堂や病院の食堂のような色気のない場所ではダメで、 ひとの温もりと手入れされている生き […]…
だからいつでもそんな気分になるのは、仕方がないことだっていうのを、 いい加減知らなければいけない。 イタリア人の彼と、クイーンズボロのアパートの窓から見たあの煌々とした明け方の月を、忘れることができないまま、 私は、またタイムトラベルに出たまま永遠に道に迷うのだ。 空の上で、いったりきたりする時間を早送りしたり巻き戻りしたりしながら 到着したのは自分の生まれ育った国だった。 でも、わ […]…
冬に近づく。 吐く息はいつのまにか白く ぐっと心を静にせざるを得なくなる。 無に、真に、透明に近づけば近づくほどみえるものはあって さすがに冬という季節がもつ 計り知れない神々しい深みと高みに圧倒されてしまう。 わたしはその前でこうして足を踏ん張って 「お願いだから」とひれ伏して どうかわたしをその真っ白な流れのなかに くわえてもらえるように 身を任せてやっとの思いで その季節の ち […]…